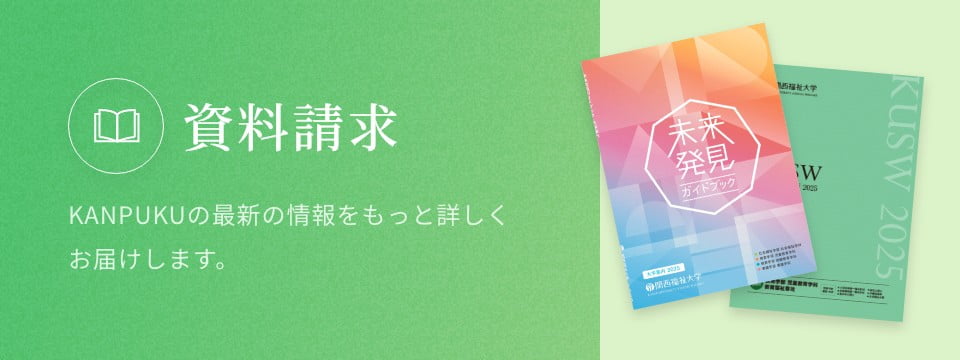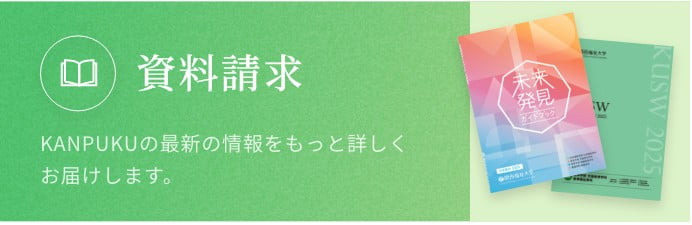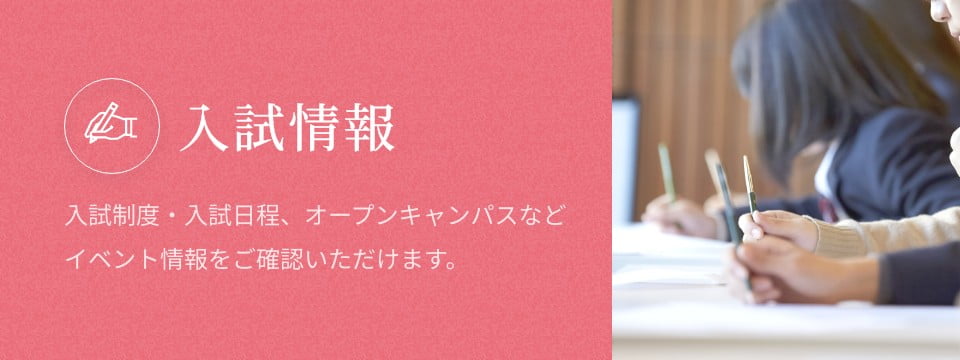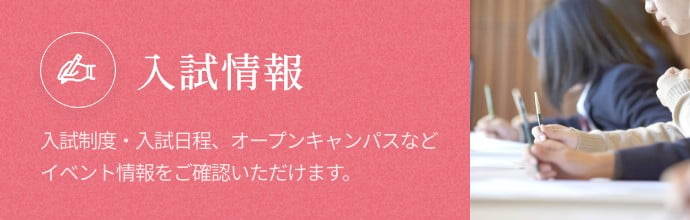[ 教育学部 児童教育学科 ]
初等教育専攻
- 取得できる資格・免許
-
- 小学校教諭一種免許状
- 幼稚園教諭一種免許状
- 保育士
- 認定心理士
- 准学校心理士
- 児童指導員
- 社会福祉主事
- 活躍できるフィールド
-
- 小学校
- 教育系企業
- 一般企業
- 大学院進学など
 学びのポイント
学びのポイント

 学生一人ひとりに応じた
学生一人ひとりに応じた
きめ細かな指導
各教科の基礎的な知識と技能を修得するとともに、児童理解力、教材開発力、指導力を養います。すべての科目できめ細かな指導を行います。

 興味を深く掘り下げ、
興味を深く掘り下げ、
専門
知識を修得する演習(ゼミ)
少人数制の演習(ゼミ)では、小学校教育に関する専門的な内容の修得をねらいとして、文献の講読やレポ ト作成、ディスカッションなどに取り組んでいます。また、自ら設定したテーマについて理解を深め、独自の考察を行なっていきます。
さらに効果をUP!

志塾(独自の学習会)
授業以外の時間を使って、採用試験対策に的を絞った勉強会を実施。2年次以降に参加できます。

朝学習
教職教養の問題を中心に朝8時から実施し、学習習慣を身につけます。学年関係なく参加できます。
その他
-
実技指導
(描画、体育実技、ピアノ実技)
-
面接指導
(集団討論、集団面接、個人面接)
-
直前対策講座
 初等教育専攻
初等教育専攻
カリキュラム
認定心理士を取得した教員を
めざせる
「心理」 「教育」をテーマに、
幼児期から思春期を体系的に学ぶ
小学校の6年間は、心身ともに大きな変化を経験する時期です。また、成長度合いは個人によって大きな差があります。これらのことを理解し、授業や日頃の生活指導にどう活かしていくか。そのために必要となるのが、心理学と教育学という2つの分野からのアプローチです。
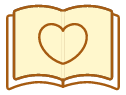
- 心理学概論
- 心理学基礎論
- 教育心理学
- 保育の心理学
- 発達心理学
- 社会心理学
- 臨床心理学
- 認知心理学
- 心理療法
- 心理測定法
- 心理学基礎実験
- 心理検査法実習
- カウンセリング概論
- 青年期の発達心理
 初等教育専攻の授業
初等教育専攻の授業
これからの未来を生きる
子どもたちを育てる教育方法を学べる


キーワードは「じぶんごと」の学び!すべての子どもたちの可能性を引き出す先生をめざす
-
個別最適な学び
自分に合うように学習を調整し、基礎的な知識や考えたり表現したりする力や、粘り強く学ぶ態度を身につけます。
-
協働的な学び
探究的な学習や体験活動を通じて、友だちだけでなくさまざまな人とコラボレーションして学び、社会の創り手となる力を身につけます。
POINT!
リアルな体験とICT活用
一人ひとりに応じた学習活動を効果的に進めるにはICT機器を活用し、学習の状況の把握や多様な教材の提供が効果的になります。一方、リア ルな体験も大切に。Al技術が発達するSociety5.0時代にこそ、自らの感覚や行為を通して学ぶことの重要性は増しています。
授業のなかで子どもの変容が感じ取れる学びを展開


教員には、子どもの心理や行動に関する深い知識が不可欠です。同時に、授業などで子どもたちを指導する、プロの技術も求められます。これら2つの要素を身につけることで、子どもたちに安心感を与え、信頼される先生として活躍することができます。


子どもは何に驚き、何を不思議に思う?
子どもの反応をイメージする
例えば、燃えている炎を見て子どもはどのように反応するのかをイメージ(予測)します。「明るい」「熱い」「揺れている」「輝いている」など、年齢に応じて異なる反応を見せます。これは、これまでの体験からさらにイメージを膨らませるからです。


授業のねらいは?展開は?
指導者としての役割をイメージする
燃える炎を見せることで、何を子どもたちに伝えたいのか。子どもの反応に対して、先生はどんな言葉を返すのか。授業で行われる子どもとのやり取りをイメージしながら、授業の「ねらい」へと子どもたちを導きます。


豊富な模擬授業を通して、
子どもたちと
協働する現代の指導法を身につける
教える内容が決まっており、ひとつの答えに導いていくのが教員であり、授業であるといったイメージから、子ども自身の体験から生まれる言葉を用いて考えを作っていく授業づくりをめざします。このような授業イメ ージをもつために、子どもの論理発達に合わせ た模擬授業を行って、指導法を身につけていきます。
-
事前学習(4月〜7月)
実習生としての心構えや実習の進め方の他、板書の仕方や指導案づくりを学びます。
-
実習(9月〜10月)
実習期間は4週間(20日間)。実習先の小学校によっては運動会や遠足などの学校行事を体験することができます。
-
実習報告(11月〜12月)
実習での経験を整理し、学内で発表をします。他の学生の体験にもふれることで、教員としての視野を広げていきます。
実習のねらい

 先生の仕事・子どもの行動・
先生の仕事・子どもの行動・
学校の活動を知る
学習指導や掃除などの生活指導、そこにおける先生や子どもたちの行動を観察します。先生という立場から1日の流れや関わり方を学びます。

 先生の仕事・子どもの行動・
先生の仕事・子どもの行動・
学校の活動を理解する
観察し、流れを把握した活動に対して、その意味やねらい、より良く行うための方法を考えます。子供の輪のなかに入り、ともに行動して過ごします。

 先生の仕事を実践する
先生の仕事を実践する
実際に授業を行ったり、子どもとともに活動を行うことで先生の仕事を実体験します。これまでに観察し、理解を深めてきた内容を実践するステップです。

 先生としての自覚を深める
先生としての自覚を深める
ひとつの授業だけでなく、子どもたちが登校してから下校するまでの間に必要なすべての役割を担当。「学級担任」を経験し、先生としての自覚を深めます。
実習の特色

 4年間にわたって計画的に実習と演習を実施。
4年間にわたって計画的に実習と演習を実施。
学内外での学びを効果的に連動させながら
実践力を磨く

 地域と連携して学ぶ
地域と連携して学ぶ
小学校は地域の個性が表れやすく、保護者だけでなく地域住民全体とのつながりが深いという側面をもちます。そこで教育実習は、赤穂市をはじめとした近隣地域の教育委員会と連携して実施。地域の特性や地域ごとの課題を把握し、それらに即した子どもとの関わり方を学んでいきます。
主な実習先
各教育委員会より、地域の小学校に配属されて実習を行います。
- ※年度により異なります
- 兵庫県
- 赤穂市、上郡町、相生市、たつの市、姫路市、加古川市、神戸市、高砂市、宍粟市、佐用町
- 岡山県
- 備前市、倉敷市