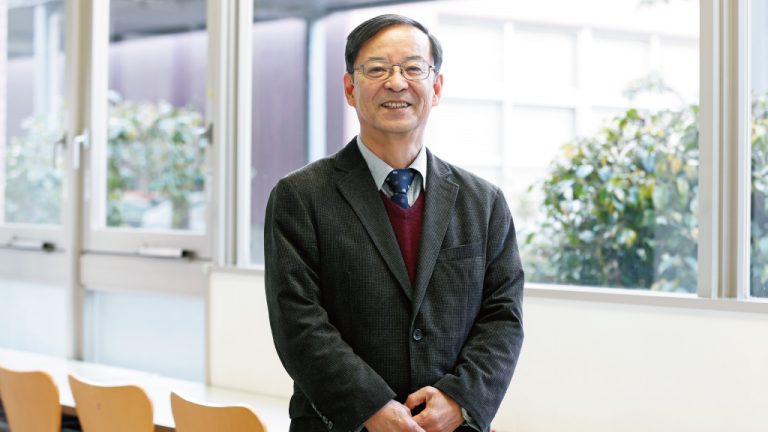忘れられない自閉症児との出会い
私が「児童相談所」に勤めている時の話です。
当時、アメリカのベッテルハイム博士は、「自閉症とは、冷たく拒否的で冷蔵庫のような心をもった母親(冷蔵庫マザー:refrigerator mother)に対して、心を閉ざしてしまった子どもの『情緒障害』である」と言っていました。
私は週1回、自閉症の5歳の女の児に「プレイセラピー(心理療法の一つで遊戯療法とも言う)」を行っていました。
非指示的・絶対受容的な態度で関わっていましたが、なかなか行動が改善せず、悩んでいました。
そんな折、上司から「やる気があるのなら家庭に入りなさい」と言われ、保護者の了解を得て家庭に入りました。
それから丸4年、月曜日から金曜日までの家庭療育が始まりました。
女の児の言葉はオウム返しのみでコミュニケーションはとれず、少しでも意にそぐわないと「パニック(奇声、顔をひっかくなど)」を起こし、家族は途方に暮れていました。
私は「生活療法」を行いました。非指示的・絶対受容的な態度ではなく、何をすべきかをわかりやすく明確に伝え、パニックを起こしても、淡々とすべきことをやらせるというものです。
日課として、マラソン、食事、入浴、就寝指導を行いました。
指示がなかなか通らず、悪戦苦闘の日々が続きましたが、ある日の食事指導を契機に指示が通りやすくなりました。
その食事指導は、女の児が食べるのを拒否し、奇声をあげ、自分の顔をひっかいても、私の腕に嚙みついても、食べさせるというものでした。
女の子が完食した時には、女の子を褒めちぎりました。
その時の様子は今でも鮮明に覚えています。
私の腕にはその時に噛まれた歯形がくっきりと残っています。
それまでは、家族や周りの人は女の児がパニックを起こすと、女の児のしたいことを許してしまうという状態でした。
それでは、社会に適応できません。
その後、小学校に入学し、文字や計算などの学習指導が生活療法に加わりました。
私は女の児との関わりを通じて、「忍耐・根気・体力」が大切なことを学びました。
RELATED POST関連記事
-
2020/07/17 総合福祉コース「大切なこと」をスケッチする⑤ ―難病の人に学ぶ―今年、授業の一環として難病患者の人へのソーシャルワークを学んでいます。 難病とは、 ①... [...続きを読む]
-
2022/06/24 こども福祉コースいつマスクを外せるか~日本人の同調圧力を考える~Withコロナでどのように過ごすか 全世界で猛威を振舞うコロナ感染が始まって3年目にな... [...続きを読む]
LATEST POST最新の記事
-
2024/04/24 総合福祉コース本学伝統のコミュニティアワーのテーマに関する覚書(後編)本学が開学以来、毎年恒例となっているコミュニティアワー報告会の(対面でおこなわれた)2... [...続きを読む]
-
2024/03/03 スポーツ福祉専攻日本で唯一!関福大の「スポーツ福祉学」とは?従来、スポーツと福祉の関わり方と言えば、アダプテッドスポーツ、障がい者スポーツ(パラスポーツ)、リハ... [...続きを読む]
-
2024/02/09 社会マネジメント専攻なぜ社会福祉学部で政策やビジネスを学ぶのかタイトル、2024年4月から関西福祉学部社会福祉学部社会福祉学科では、新たに社会マネジメント専攻が立... [...続きを読む]