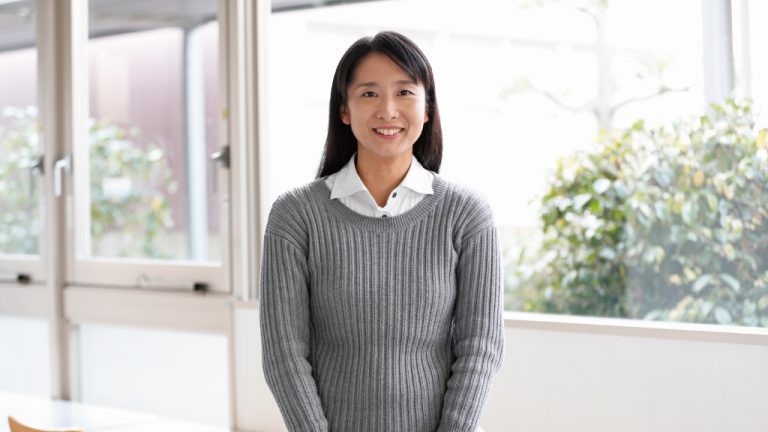災害ボランティアと受援力
1995年の阪神・淡路大震災では、死者約6,434人という大きな被害がありました。
そして震災で被災した方へ支援するために、1995年から約1年間に約137万人がボランティア活動をしており、その様子を新聞やニュースなどのメディアによく取り上げられたことから、その年を「ボランティア元年」と呼ぶようになりました。
その後の東日本大震災、熊本地震等でも全国から多くのボランティアが現地を訪れ、支援活動を行っています。
私のゼミでは、学生たちが被災した地域における支援活動を企画し実践する活動を行っています。
前期に企画準備、ボランティア活動先との電話調整、夏季休暇中には実践活動、後期には活動の振り返りという年間を通したスケジュールで取り組みます。
2019年度は、熊本地震で被災した方の心のケアを目的に、障害者支援施設、幼稚園、児童クラブ、仮設住宅・災害公営住宅等を訪問し、交流活動を行いました。また、地震で困ったこと、どのような支援活動を行ったのか等について学生がインタビューも行い、特に災害時要配慮者の視点における災害復興支援への理解を深めています。
学生がインタビューする中で、特に印象に残っているのは、被災された方から伺う「受援力」という言葉です。
「受援力」とは、公的機関からの支援だけではなく、地域住民、ボランティアなども含めて支援を受け入れる力のことです。
現地の方からは、日頃から外部とのつながりを持っておく重要性を繰り返し聞く機会がありました。
「受援力」は言い換えると、様々な属性の人と協働し物事を成し遂げる力なのかもしれません。
有事の時こそ、分野の隔たりを超えて様々な人と協力して困難を解決する必要があります。
災害ボランティアに勤しむ学生には、活動を通して「様々な属性の人と協働し物事を成し遂げる力」を磨いてほしいと願っています。
RELATED POST関連記事
-
2021/01/20 こども福祉コースコロナ渦でも学生が頑張ったこと!その① ~「第9回子ども支援セミナー」の開催~昨年は新型コロナに翻弄された一年でした。 本学でも卒業式、入学式が中止になりました。 ... [...続きを読む]
-
2020/05/01 医療福祉コース勝田吉彰研究室のコラムはじまりますこれまで臨床医・外務省医務官・産業医・大学での経験を活かしながら、海外赴任者の健康管理や国境を越える... [...続きを読む]
-
虐待を受けた子ども達を支援する第1回 人を支援するということ 本稿では「虐待を受けた子ども達を支援する」ということをテーマに、思い... [...続きを読む]
LATEST POST最新の記事
-
2024/04/24 総合福祉コース本学伝統のコミュニティアワーのテーマに関する覚書(後編)本学が開学以来、毎年恒例となっているコミュニティアワー報告会の(対面でおこなわれた)2... [...続きを読む]
-
2024/03/03 スポーツ福祉専攻日本で唯一!関福大の「スポーツ福祉学」とは?従来、スポーツと福祉の関わり方と言えば、アダプテッドスポーツ、障がい者スポーツ(パラスポーツ)、リハ... [...続きを読む]
-
2024/02/09 社会マネジメント専攻なぜ社会福祉学部で政策やビジネスを学ぶのかタイトル、2024年4月から関西福祉学部社会福祉学部社会福祉学科では、新たに社会マネジメント専攻が立... [...続きを読む]