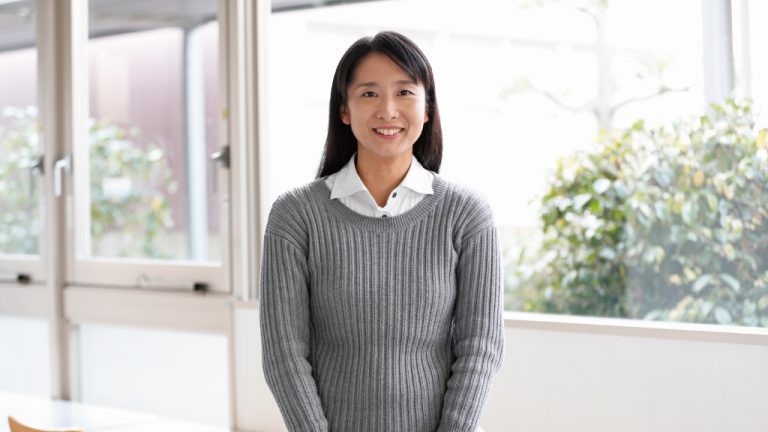「障害当事者の声」の政策反映
2006年に国連総会において、障害者権利条約が採択されました。
障害者権利条約とは障害者の権利を実現するために国で行うべきことが決められてあり、2014年に日本も締結しています。日本では条約の内容をさらに具体的に取り組んでいくために、2016年に障害者差別解消法を施行し、同法では障害者の不当な差別的取り扱いの禁止と合理的配慮の提供について規定しています。
その障害者権利条約をつくる過程の中でも注目したいのは、障害当事者たちのスローガンであった「私たち抜きに私たちのことを決めないで(Nothing About Us Without Us)」という考え方です。
ここでいう「私たち」とは障害当事者のことであり、障害者権利条約も障害当事者の参加がある中で作られました。つまり、政策策定過程に障害当事者の参加・参画があることを求めています。
障害者福祉の歴史を振り返ると、障害当事者の声によって生活のしづらさが変わった例は多くあります。例えば、現在はノンステップバスが普及し、車いすを利用している方がバスに乗車するのは当たり前に目にする風景だと思います。
しかし、1970年代頃は、車いすを利用している人はバスの物理的な問題もあり、介助者なしにはスムーズに乗車することができませんでした。それに対して、「おかしい」と感じた障害当事者たちが、介助者なしでも乗車できるように全国の様々な地域で声をあげ、暮らしやすいまちづくりが進められてきた一面もあるのです。
現在は、障害当事者が政策策定過程に参加・参画する仕組みが以前よりも作られるようになってきました。例えば、地方自治体が策定する障害福祉計画・障害者計画に委員として障害当事者が参加するといったことです。
しかし、現在の様々な仕組みが十分に活かされているか、まだ明らかになっていないこともあります。
そのため、「障害当事者の声」を政策に反映することのできる仕組みづくりの研究に私は取り組んでいます。
RELATED POST関連記事
-
2020/06/04 総合福祉コース「新型コロナと福祉思想」その1―ICT社会としんがりの思想―新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため大学でもオンライン授業が中心となり、会議もZoomが使われてい... [...続きを読む]
-
2021/09/01 総合福祉コース適性は形成概念:あなたは向いている? それとも向いていない?看護にしても社会福祉にしても、その仕事に向いているか向いていないか、この適性の問題は大... [...続きを読む]
LATEST POST最新の記事
-
2024/04/24 総合福祉コース本学伝統のコミュニティアワーのテーマに関する覚書(後編)本学が開学以来、毎年恒例となっているコミュニティアワー報告会の(対面でおこなわれた)2... [...続きを読む]
-
2024/03/03 スポーツ福祉専攻日本で唯一!関福大の「スポーツ福祉学」とは?従来、スポーツと福祉の関わり方と言えば、アダプテッドスポーツ、障がい者スポーツ(パラスポーツ)、リハ... [...続きを読む]
-
2024/02/09 社会マネジメント専攻なぜ社会福祉学部で政策やビジネスを学ぶのかタイトル、2024年4月から関西福祉学部社会福祉学部社会福祉学科では、新たに社会マネジメント専攻が立... [...続きを読む]