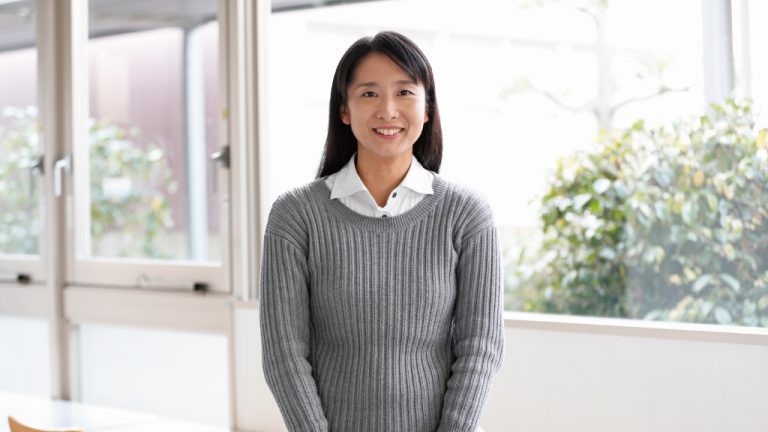ボランティアから得られるもの(前編)
大学に入ったら始めてみようと思うことに、「ボランティア」を挙げる学生さんがいます。
ボランティアという言葉は、ラテン語の volo(ウォロ)が語幹であり、日本語で言うと「自発性」が中核概念となった言葉で、誰から言われて行うものではなく自ら行うものです。
ボランティアは原則無償で行われるものですが、今回はボランティアの支援を受け入れる側の視点で、ボランティアから得られるものを考えてみたいと思います。
以前のコラムでも書きましたが、私のゼミでは災害・復興支援活動の支援活動を企画し、学内の誰もが参加できるボランティア活動を実施しています。ある年、地震で被災し仮設住宅に住まわれている方と楽しく交流する活動を行った時のことです。
ある学生が仮設住宅に入居されている方から、このような話を聞かせて頂きました。
(※原文をわかりやすいように一部加工しています)
―――仮設住宅に住んで、毎日 TV 見たり、新聞を読んだり、家で過ごしていることが多い。
毎日が同じことの繰り返しだが、ボランティアの人が来てくれることによって日常生活が変わるんだ。
だからボランティアの人が来るのを楽しみにしているんだ。―――
ボランティアの支援を受け入れる側の方は、ボランティアと接することによって「生活の楽しみ」が生まれ、「日常生活の変化」が生まれるということをお話ししてくださいました。
ボランティアは前提として相手のために行うものなので、相手に喜んでもらえることが大切であると思います。
ボランティアを始めたいなと思った時に、「自分にはできるかな?」とその一歩を踏み出すのに勇気がなかなか出ない方もいると思います。
しかし、一般的なボランティア活動は、特別な知識や経験が必要ありません。
ただその場に行って相手とお話しするだけでも、相手にとって意味を持つのです。
(後編に続く)
RELATED POST関連記事
-
2021/02/19 総合福祉コース「ソーシャルワークって何だろう?」--ソーシャルワークで、社会をプロデュースする!「ソーシャルワークって何だろう?」 社会や地域の中で起こっているさまざまな課題を解決す... [...続きを読む]
-
2021/01/20 こども福祉コースコロナ渦でも学生が頑張ったこと!その① ~「第9回子ども支援セミナー」の開催~昨年は新型コロナに翻弄された一年でした。 本学でも卒業式、入学式が中止になりました。 ... [...続きを読む]
-
2022/02/28 総合福祉コース人間一人ひとりに、等しくある「尊厳」 ~「津久井やまゆり園」事件後のソーシャルワーク教育~2016年、神奈川県にある知的障害者施設「津久井やまゆり園」で、元職員が施設に侵入し、... [...続きを読む]
LATEST POST最新の記事
-
2024/04/24 総合福祉コース本学伝統のコミュニティアワーのテーマに関する覚書(後編)本学が開学以来、毎年恒例となっているコミュニティアワー報告会の(対面でおこなわれた)2... [...続きを読む]
-
2024/03/03 スポーツ福祉専攻日本で唯一!関福大の「スポーツ福祉学」とは?従来、スポーツと福祉の関わり方と言えば、アダプテッドスポーツ、障がい者スポーツ(パラスポーツ)、リハ... [...続きを読む]
-
2024/02/09 社会マネジメント専攻なぜ社会福祉学部で政策やビジネスを学ぶのかタイトル、2024年4月から関西福祉学部社会福祉学部社会福祉学科では、新たに社会マネジメント専攻が立... [...続きを読む]