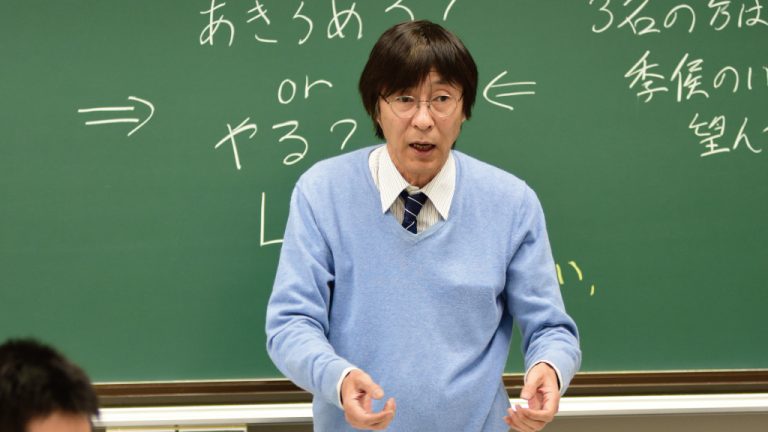家族は頑張るべき存在か ~自己責任論・家族責任論の怖さ~
認知症の高齢の方を支援している息子さんやその配偶者の方に対し、また、障害のある方を支援している高齢の親の方に対し、私たちは「大変ですね」「頑張ってくださいね」「お身体を大事になさってくださいね」という言葉をかけ、励ましていることが一般的に見られる光景かと思います。
しかしながら、「なぜあなたが頑張る必要があるのですか」という言葉を聞くことはほとんどないのではないでしょうか。
前者の言葉かけは、一聴すると優しさにあふれたものですが、これらの励ましの言葉をいつも聞かされる家族をして、「私が頑張らないと」と追い込んでいることに気付くことはほとんどないと思います。そして、頑張ることを周囲や社会から期待され続けた家族がやがて(身体的・経済的・精神的に)限界を迎えた時、かつての愛情にあふれた支援が放置に、そして深刻な虐待へと変化してしまうことがあります。
そして、虐待が起きた時、私たちは手のひらを反すように「ほとんどの人はそんなことをしないのになぜ」として、虐待に及んだ家族に責を求めることはあっても、社会の欠陥に目を向ける動きは弱いままです。
これが交差点の事故であればどうでしょうか。
事故の多い交差点があったとき、私たちは事故を起こしたドライバーを責めるのではなく、交差点の形状等に問題があるとして、一旦停止の標識や信号機の設置、道路形状の改良など、「人」ではなく「環境」に事故の要因を求め、その解消に向かいます。
この対応と、虐待に対する対応が全く矛盾していることをどれだけの人が自覚しているでしょうか。
高齢の方や障害のある方に自分の人生を謳歌する権利があるのと同様に、家族にも当然にしてご自身の人生を楽しむ権利があります。支援に対し、ご家族が心からそれを望んでいるのでない限り、自分の人生や時間を犠牲にして支援に従事する必要は少しもありませんし、社会の価値観(もはや偏見と言ってよい)によって無形の圧力が加えられている状況を変えていく時期に来ています。
自己責任論・家族責任論・・・これらは時として優しさの衣をまといつつ、冷酷な仕打ちをしてしまうことに気を付けなければならないと思います。
RELATED POST関連記事
-
2020/07/17 総合福祉コース「大切なこと」をスケッチする⑤ ―難病の人に学ぶ―今年、授業の一環として難病患者の人へのソーシャルワークを学んでいます。 難病とは、 ①... [...続きを読む]
-
2020/05/18 医療福祉コースカナダ バンクーバー研修記(前編)昨年の夏、私は海外研修(カナダ バンクーバー)引率の機会をいただきました。 研修は、夏期休暇期間中の... [...続きを読む]
-
2021/01/19 総合福祉コースコミュニティによい実践② ~観光スポットの分析~2018年10月、『兵庫県赤穂市GAP調査報告書』が公表されました。 この報告書は全9... [...続きを読む]
LATEST POST最新の記事
-
2024/04/24 総合福祉コース本学伝統のコミュニティアワーのテーマに関する覚書(後編)本学が開学以来、毎年恒例となっているコミュニティアワー報告会の(対面でおこなわれた)2... [...続きを読む]
-
2024/03/03 スポーツ福祉専攻日本で唯一!関福大の「スポーツ福祉学」とは?従来、スポーツと福祉の関わり方と言えば、アダプテッドスポーツ、障がい者スポーツ(パラスポーツ)、リハ... [...続きを読む]
-
2024/02/09 社会マネジメント専攻なぜ社会福祉学部で政策やビジネスを学ぶのかタイトル、2024年4月から関西福祉学部社会福祉学部社会福祉学科では、新たに社会マネジメント専攻が立... [...続きを読む]