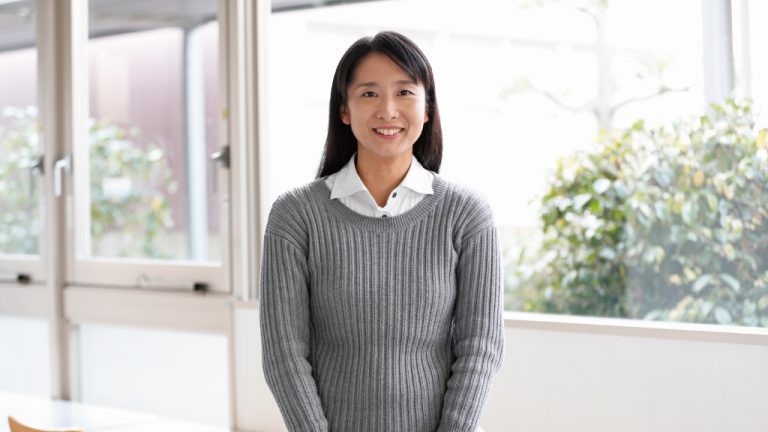研究と福祉実践の共通点
大学教員の仕事の一つに研究活動があります。
そして、大学生のみなさんも卒業論文に取り組まれます。
大学は研究機関であり、研究によって生まれる新しい発見や価値を発信する場所だと思っています。
今回のコラムでは、その研究活動のエピソードとして、私が思う研究と福祉実践の共通点について紹介したいと思います。
まず初めに、研究をする時には、テーマを決めて計画を立てます。
どのような研究をするのかを思いを巡らせる時に、自分の経験から生まれる問題意識を大切にしています。
私の場合は、福祉の実践の現場に足を運んで、障害当事者や支援者と話すことでテーマが見つかることが多いです。
現場で見つけたテーマの場合は、そこで感じたこと、疑問に思うことをベースに、研究の全体像を考えていきます。
卒業論文に取り組む学生のみなさんも「テーマを何にするか」が最初の大きな壁のようです。
これまでの学生さんの取り組みを振り返ると、ソーシャルワーク実習やゼミ活動、ボランティア活動で生まれた問題意識をもとに取り組んでいる方も多く見られます。
最近では、障害者福祉政策に関する全国アンケート調査を行いました。
回収したアンケート調査の結果をまとめながら回答されている記述を読むことを通して、アンケートに書かれている言葉の背景について考え、答えてくださった方の思いを想像します。
このことは、福祉の実践にも通じることがあると私自身は感じています。
福祉の実践でも、相手がどのように思っているのか、感じているのかを想像しながら関わります。
相手の世界に入り、相手のことをよく考えるという点は、研究と福祉実践の共通点だと私は思います。
研究は必ずしも順調に行かないこともあり、思い通りにいかず苦労することもあります。
しかし、新しい発見や価値が感じられることが見つけられた時は、これまでの苦労も報われて喜びもひとしおです。
意義ある研究をすることで、社会に貢献していきたいと考えています。
RELATED POST関連記事
-
2020/11/27 総合福祉コース大切なことをスケッチする⑨ ー学生たちが宿している知性と大学教育の基本ー授業の中で、時々、学生たちの素晴らしい知性や感性に感銘を受けることがあります。 その一... [...続きを読む]
LATEST POST最新の記事
-
2024/04/24 総合福祉コース本学伝統のコミュニティアワーのテーマに関する覚書(後編)本学が開学以来、毎年恒例となっているコミュニティアワー報告会の(対面でおこなわれた)2... [...続きを読む]
-
2024/03/03 スポーツ福祉専攻日本で唯一!関福大の「スポーツ福祉学」とは?従来、スポーツと福祉の関わり方と言えば、アダプテッドスポーツ、障がい者スポーツ(パラスポーツ)、リハ... [...続きを読む]
-
2024/02/09 社会マネジメント専攻なぜ社会福祉学部で政策やビジネスを学ぶのかタイトル、2024年4月から関西福祉学部社会福祉学部社会福祉学科では、新たに社会マネジメント専攻が立... [...続きを読む]