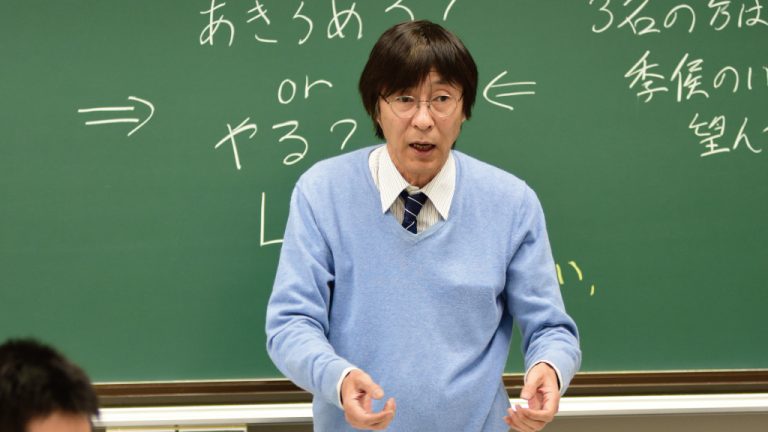人を人として見れなくなる福祉教育の弊害
福祉に関して学生と接していて気を付けていることがあります。
それは知識や技術を重視しすぎることで起きがちな「専門バカ」を生み出さないために何が必要かということ、そのための片方の重しをどのように提供していくかという点です。
興味深い変化があります。
一枚の写真を学生に見せます。
その写真は、四肢麻痺があり、気管切開もしていて、知的にも障害があると思われる5歳くらいのこどもが車いすに座り、横に母親が付き添っているものです。
この写真を見せて、
①「最初に」どこに意識が行くか
②「最初に」どんな言葉かけをするか
を学生に問うと、2年生あたりでは、ABの答えが半々くらいですが、4年生になるとAが8割、Bは2割と大きく変化しています。
Aの答えは①「四肢ともに麻痺があり、動かすのは難しい」「気管切開なので発語も難しい」など
また、②「最初にお母さんに状況をお伺いしてからこどもさんに声をかけます」などです。
これがいわゆる「専門バカ」の答えであり、知識や技術が根本となる理念がないまま蓄積されてしまった典型例だと考えています。
では、2年生の時に約半数もあったBの答えは、
①「5歳くらいにしては大柄かな?」「顔色もよくてつやつやしているなぁ」
②はこどもさんに直接「普段どんなテレビ見てる」「どんな遊びしてる」などです。
もうおわかりのように、障害児は障害が先か、こども(児)が先か、ということであり、生の言葉でいえば「障害があるとかないとか、そんなもんは「最初」はどっちでもええんじゃ!5歳は5歳じゃ!」ということではないでしょうか。
これを見失わせてしまう福祉教育であれば、いかに高尚なことや実践的な知識・技術を伝えたとしても全くの無意味であり、そればかりか弊害だらけのものとなってしまいます。
人を人としてとらえる、「最初に」人を全体として見る(ピープル・ファースト)、専門バカになることなく、当たり前に普通の感覚をもった専門職が増えていくことを願って、学生とくだらない雑談にふける毎日です。
RELATED POST関連記事
LATEST POST最新の記事
-
2024/04/24 総合福祉コース本学伝統のコミュニティアワーのテーマに関する覚書(後編)本学が開学以来、毎年恒例となっているコミュニティアワー報告会の(対面でおこなわれた)2... [...続きを読む]
-
2024/03/03 スポーツ福祉専攻日本で唯一!関福大の「スポーツ福祉学」とは?従来、スポーツと福祉の関わり方と言えば、アダプテッドスポーツ、障がい者スポーツ(パラスポーツ)、リハ... [...続きを読む]
-
2024/02/09 社会マネジメント専攻なぜ社会福祉学部で政策やビジネスを学ぶのかタイトル、2024年4月から関西福祉学部社会福祉学部社会福祉学科では、新たに社会マネジメント専攻が立... [...続きを読む]