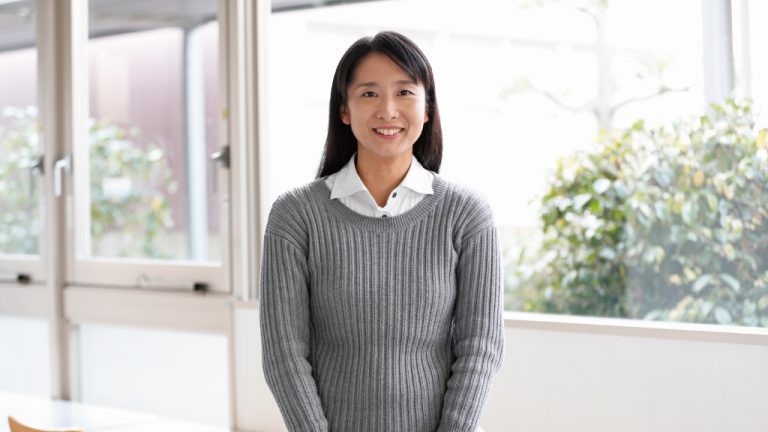僕の歩く道
「僕の歩く道」は2006年に放送されたドラマで、自閉症の30代の青年である大竹輝明さんが主人公である。
少し古いドラマであるが、今観ても多くの学びや気づきが得られる。
大竹さんは職場での人間関係がうまくいかずに退職して仕事が無かったことから、幼馴染の勧めにより幼馴染が勤める職場である動物園の飼育係として働くことになる。
ドラマを観ていると、支援の大切なポイントがいくつも見て理解することが出来る。
例えば、主人公の大竹さんは記憶力に優れておりルーティンワークの仕事は行うことができるが、その一方で臨機応変な対応には苦手さがある。
そのため、職場では周囲とのコミュニケーションがうまくいかずに、大竹さんは体調を崩してしまう場面もあった。
しかし、本人の特徴をよく理解する幼馴染が同僚へアドバイスを行うことと、そして同僚が大竹さんとコミュニケーションを重ねていく中で徐々にどのようにしたら一緒に働けるか、理解を深めていく。
このことから、ご本人を理解しながらコミュニケーションの工夫を図ることの大切さを学ぶことが出来る。
そして、ドラマの中でも印象的なのは、同僚の飼育係の古賀さんのエピソードである。
古賀さんの子どもも自閉症であるが、父親として子どもに向き合うことが出来ず、そのことを理由に離婚に至り子どもとも数年会っていない。
しかし、大竹さんと一緒に仕事をする中で理解を深めていき、子どもにもう1度会いたいという気持ちに変化し、最終的には子どもと会うことができた。大竹さんと一緒に働くことで、古賀さんは自分の子どもと向き合うことができたのである。
このことから、大竹さんと一緒に働くことの意義深さを感じられるのではないだろうか。
ドラマの後半では、大竹さんは徐々に職場にも馴染み、人間関係を築きながら職場でもできる仕事が徐々に広がっている様子を見ることができる。
また、家族の金銭管理のサポートを受けながら給料を貯金して、趣味のロードバイクを買って楽しんでいる場面もあった。大竹さんは感情が表情に出にくいという特徴があるが、心なしか穏やかな表情に変化しているように見える。
このドラマを通して、大竹さんが周囲との関わりが増えることで、様々な可能性が広がっていく様子をみることができる。
そのような可能性を広げていくきっかけをつくることがソーシャルワーカーの大切な役割なのだと思う。
「僕の歩く道」がより豊かに、より楽しく歩けるように。
RELATED POST関連記事
LATEST POST最新の記事
-
2024/04/24 総合福祉コース本学伝統のコミュニティアワーのテーマに関する覚書(後編)本学が開学以来、毎年恒例となっているコミュニティアワー報告会の(対面でおこなわれた)2... [...続きを読む]
-
2024/03/03 スポーツ福祉専攻日本で唯一!関福大の「スポーツ福祉学」とは?従来、スポーツと福祉の関わり方と言えば、アダプテッドスポーツ、障がい者スポーツ(パラスポーツ)、リハ... [...続きを読む]
-
2024/02/09 社会マネジメント専攻なぜ社会福祉学部で政策やビジネスを学ぶのかタイトル、2024年4月から関西福祉学部社会福祉学部社会福祉学科では、新たに社会マネジメント専攻が立... [...続きを読む]