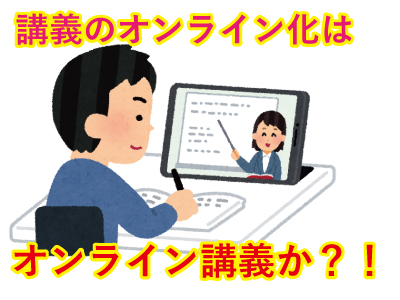「講義のオンライン化」は「オンライン講義」か①
新型コロナの影響で日本全国の大学ではオンライン講義が行われています。
本学では6月になり一部対面授業が開始されたものの当面はこのような状況が続くかもしれません。
少なくとも後期も「オンライン講義」が継続されるようです。
今回はこのオンライン講義について前期を振り返りつつ、これからどう取り組むべきなのかを考えてみましょう。
ちょっとシリーズ化を目指してみるのも面白そうです。
このオンライン講義の取り組みは教員の苦悩と言っても良いでしょう。
ただし、私は教育に携わっているものの、教育の専門家ではありません。一実践者としての意見として読んでいただければと思います。
まず、概念の整理です。オンライン講義は、以下の3つに分類されます(文部科学省による定義)。
①同時双方向型
②動画配信(オンデマンド)型
③課題探求型
オンライン講義はこの中の一つを選択して実施することになります。
加えて、このいずれにおいても学生が質問や議論できる機会を設けることが必須となります。
これまでの対面講義では特に意識しなくてもできていたことを意識的に取り組まなければいけなくなった感じですね。
私は主に①と②に取り組みました。今回はまず全体を振り返りつつ、考えをまとめたいと思います。
さて、前期をふり返ると
「そもそもオンライン講義は従来の講義をオンライン化すれば成立するのか?」
という問いがずっと頭を悩ませていました。
そして、なんとなく「従来の講義のオンライン化ではオンライン講義にはならない」という答えにたどり着いているのが現状です。
これまでの講義は大学の教室で受講していましたが、オンライン講義になると自宅での受講となります。
この環境(空間)の変化は大きいと思います。
従来の90分の講義は教員と学生が空間を一緒にするから集中して聞くことができていたのではないかと思っています(もちろん全員が集中しているわけではないかもしれませんが)。
では、90分の講義を単純に撮影し、配信したものを視聴する時、同じように集中できるのでしょうか。
少なくとも私は集中できないでしょう。
ここに大学の教室という空間がもつ意味が存在します。
ということは講義をオンライン化するだけでは十分とは言えないのではないかと思うわけです。
そこで、オンライン講義用に講義設計を再編し、それに即したスライド構成に修正することが求められます。
つまり、90分の講義全体の構成を一から見直さなければいけないというわけです。
これが1科目につき15回分です。
そもそも大学の講義は事前学習(予習)→講義→事後学習(復習)で構成されていて、シラバスにその内容が記載されています。その講義部分は90分という厳密な時間の制約がありました。少なくともこの90分をオンライン講義用にどう構成しているのかを説明できる必要があるでしょう。
つまり、これまでの講義をオンライン用に再構築して実施してきたのが前期でした。
それも急遽決定したオンライン講義…教員も試行錯誤が続いた数ヶ月間だったと思います。
小・中・高校は緊急事態宣言下で休校となり、教育の進捗が大幅に遅れました。
一方、大学ではオンライン講義で対応したことで遅れは最小限に留められたのではないでしょうか。
もちろん前期が終えた段階でふり返ることでオンライン講義の質を考え直し、さらなる向上を目指すことになります。
こういったことを考えるきっかけになったのはFacebookページ「新型コロナ休講で、大学教員は何をすべきかについて知恵と情報を共有するグループ(https://www.facebook.com/groups/146940180042907)(秋から「新型コロナのインパクトを受け、大学教員は何をすべきか、何をしたいかについて知恵と情報を共有するグループ」に改称)」のモデレーターとして意識的に全体を見ることができたからだと思います。
多くの大学教員は悩み苦しみ、身体を酷使しながら前期のオンライン講義を乗り越えていたことでしょう。
次回は私の実際の講義を例に挙げていきたいと思います。
RELATED POST関連記事
-
2024/02/09 社会マネジメント専攻なぜ社会福祉学部で政策やビジネスを学ぶのかタイトル、2024年4月から関西福祉学部社会福祉学部社会福祉学科では、新たに社会マネジメント専攻が立... [...続きを読む]
LATEST POST最新の記事
-
2024/04/24 総合福祉コース本学伝統のコミュニティアワーのテーマに関する覚書(後編)本学が開学以来、毎年恒例となっているコミュニティアワー報告会の(対面でおこなわれた)2... [...続きを読む]
-
2024/03/03 スポーツ福祉専攻日本で唯一!関福大の「スポーツ福祉学」とは?従来、スポーツと福祉の関わり方と言えば、アダプテッドスポーツ、障がい者スポーツ(パラスポーツ)、リハ... [...続きを読む]
-
2024/02/09 社会マネジメント専攻なぜ社会福祉学部で政策やビジネスを学ぶのかタイトル、2024年4月から関西福祉学部社会福祉学部社会福祉学科では、新たに社会マネジメント専攻が立... [...続きを読む]