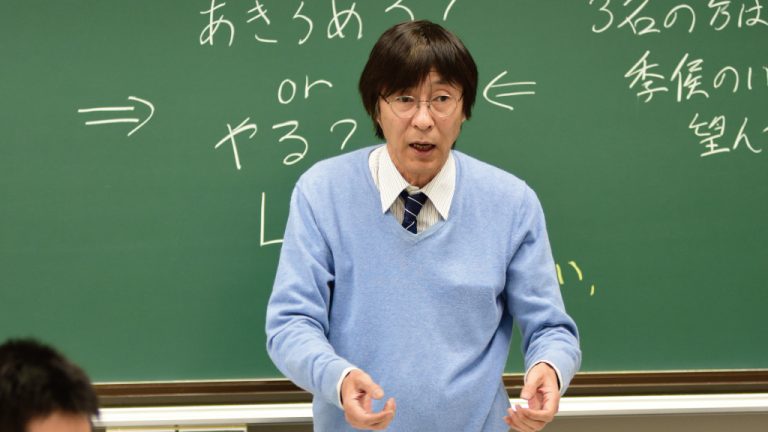「空間」と「時間」(現在の専門知識・技術教育に欠けている視点)
「共生社会」の実現と「意思決定」支援、これらは今日の福祉において、とても大事にされるべきこととして取り組まれています。
私たちの福祉も、紆余曲折を経て、ようやくここまでたどり着いたという観があります。
まず「共生社会」、これは介護や高齢者領域で国が掲げている「地域共生社会」のような狭いものではなく、まして「共生型」サービスに用いられている間違った概念でもありません。
「共生社会」で最も重要となるものは「空間(場)」の共有でなければなりません。
障害者基本法に見るように、障害のあるなしに関わらず共に生きる社会を実現することが何よりも大事なこととされています。
次に「意思決定支援」、相手の意思決定を支援するためには、時としてとても多くの時間を要しますが、この「時間」を何よりも大事にするという考えがようやく定着しようとしています。
これまでは、ともすれば専門的な知識や技術ばかりが重要視され、また、福祉の現場でもどれだけ最先端の支援技術を投入するか(できるか)が問われた時代がありました。
しかしながら、「共生社会」「意思決定支援」においては、そのような専門性以上に、「空間」「時間」の確保ができるか、しようとしているかが問われていると考えて良いでしょう。
また、この「空間」「時間」を大事にすることこそが、本当の意味での利用者主体であり、本人の尊重にほかなりません。
専門的な知識・技術が不要というわけではありませんが、このことのみを追求することは、いわゆる支援側の「傲慢」にほかならず、本人主体の支援は実現しないことに思いをはせる必要があるでしょう。
一方で、現在の大学等における専門教育には、「時間」と「空間」の双方ともが欠如して(あるいは地域共生社会や共生型サービスのように誤って)いると思われます。
しかしながら、これらは何も難しいものではなく、最も基本的なものであるとも言えます。
このことについて、学生・教員・専門職が、一度立ち止まって考える時期が来ていると考えています。
RELATED POST関連記事
-
2021/06/10 こども福祉コーススマホの利用あれこれ~コロナ禍での過ごし方~スマホ依存症が社会問題へ コロナ禍が始まる前から大学生だけではなく、中高年においても「スマホ依存症」... [...続きを読む]
LATEST POST最新の記事
-
2024/04/24 総合福祉コース本学伝統のコミュニティアワーのテーマに関する覚書(後編)本学が開学以来、毎年恒例となっているコミュニティアワー報告会の(対面でおこなわれた)2... [...続きを読む]
-
2024/03/03 スポーツ福祉専攻日本で唯一!関福大の「スポーツ福祉学」とは?従来、スポーツと福祉の関わり方と言えば、アダプテッドスポーツ、障がい者スポーツ(パラスポーツ)、リハ... [...続きを読む]
-
2024/02/09 社会マネジメント専攻なぜ社会福祉学部で政策やビジネスを学ぶのかタイトル、2024年4月から関西福祉学部社会福祉学部社会福祉学科では、新たに社会マネジメント専攻が立... [...続きを読む]